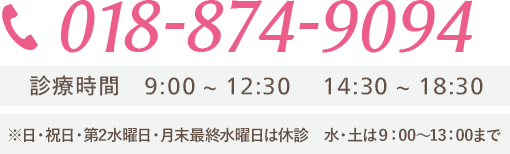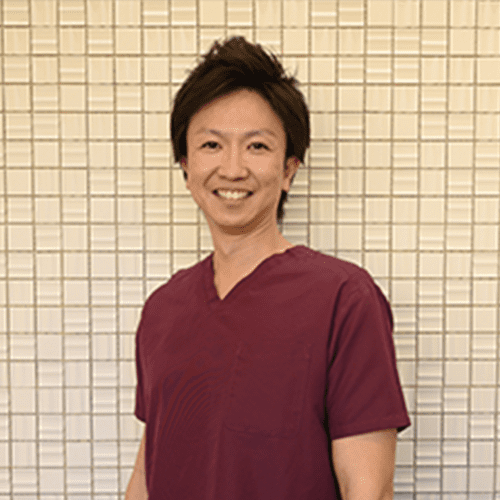奥歯の抜歯後そのまま放置は厳禁! 9つのリスクと治療・予防方法とは

こんにちは、秋田のハピネス歯科クリニック 大久保です。今回は、奥歯の抜歯後の放置についてお話します。
さまざまな事情から奥歯を抜歯したけれど、その後どうすればいいのかと悩んだ結果、そのままにしているという方が残念ながら多いようです。
抜歯で痛みの原因がなくなったため楽になる他、奥歯は人から見えにくい場所ということもあり、そのままずるずると時間が経過してしまうのでしょう。
しかし、本来あるべき歯が欠損していると、やがて全身に悪影響を及ぼします。
これから奥歯の抜歯予定がある方、昔に奥歯を抜いたけれどそのままにしているという方に向けて、この記事では奥歯の抜歯後に放置すると起こる問題や治療法などを解説します。
奥歯を抜いたあとそのままはNG! 放置するリスクとは
奥歯は単に食べ物を噛むだけのパーツではありません。本来あるべき歯が1本でも欠損していると、お口の中の精密なバランスが崩れ、最終的に全身に深刻な悪影響を及ぼします。
まずは奥歯抜歯後に放置が危険な理由や、時間を経て現れる変化について説明しましょう。
抜歯後に放置が危険な理由
奥歯は食事の際に噛む力(咀嚼力)の多くを担う、言わば「食べ物をすり潰す工場」です。奥歯が欠損すると噛む力が大幅に低下し、食事が偏ったり、大きな塊のまま飲み込んだりするようになり、胃腸に負担をかけます。
また、奥歯は顎の関節の位置を決め、顔の輪郭や噛み合わせを支える「土台」です。奥歯がない状態で噛み続けると顎の関節がズレたり、顔の筋肉の付き方が変わったりするため、顔の左右非対称化や早期の老化を招きます。
そして、歯列全体への悪影響です。歯は、上下左右の歯が互いに支え合って適切な位置に留まっています。奥歯がなくなると隣の歯が倒れ、噛み合っていた歯が伸び出してきます。歯列全体が変化すると、後の治療が非常に複雑で大がかりなものになってしまうのです。
短期・中期・長期で起こる変化
抜歯後治療を先延ばしにした場合の、時間が経つにつれて現れる変化について表にしました。
| 放置期間 | 起こりやすい変化 | 具体例・症状 |
|---|---|---|
| 〜3か月 | ・噛みにくい ・隣の歯が少し傾く | ・かみ合わせに違和感 ・食べづらい |
| 6か月〜1年 | ・対合歯が伸びる ・隣歯が倒れる | ・見た目の歪み ・歯茎の炎症 |
| 1年以上 | ・顎の骨が減る ・顔が変形する ・全身への影響 | ・顔のたるみ ・頭痛・肩こり ・消化不良 |
リスクはすぐに現れないため、そのままにしてしまいやすいのが欠損治療の難しい点です。「時間が経つほど治療は複雑化する」と覚えておいてくださいね。
【関連記事】歯がなくなると起こるトラブルについての記事はこちら
歯がなくなるとどうなる? 起こるトラブル5つと治療法3つ
【関連記事】歯がなくても生きていけるかどうかについての記事はこちら
歯がなくても生きていける? 歯がないことによって起こるリスク
奥歯の抜歯後にそのまま放置すると起こる9の問題点
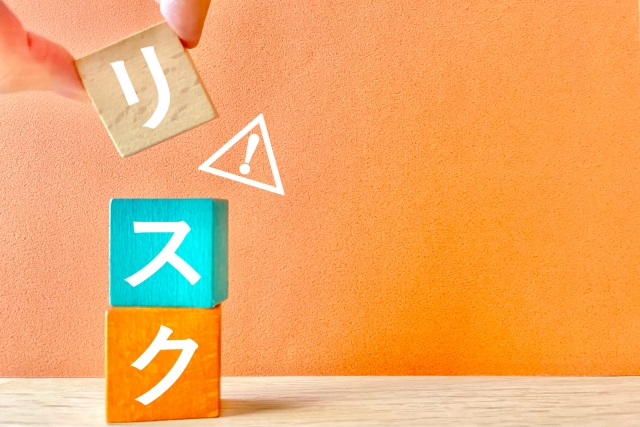
では、奥歯を抜歯したあとに放置するとどのような問題点が起きるのかについて、順番にみていきましょう。次の9個の問題が考えられます。
いずれも短期的に発生するものではなく、長い時間をかけて徐々に出てくる問題です。そのためできるだけ早く対処する方が、治療にかける時間や費用も抑えられますよ。
- ・対合歯が伸びてくる
- ・隣の歯が倒れてくる
- ・出っ歯になりやすくなる
- ・滑舌が悪くなる
- ・咀嚼しにくくなる
- ・顔の形が変わり老化が早まる
- ・全身のバランスが崩れる
- ・認知症リスクが上がる
- ・瞬発力が失われる
対合歯が伸びてくる
上下の歯は、お互いに噛み合い続けることでそこに留まれます。そのため抜歯によって上下どちらかの歯がなくなると、噛み合うはずの歯が伸びてくるのです。これを「挺出(ていしゅつ)」と言います。挺出が進行すると、伸びた歯を大きく削らなければ噛み合わせが作れず、場合によっては神経を抜く処置が必要になるなど、健康な歯を犠牲にする羽目になります。
そして、この場合の「伸びる」は歯が長くなるわけではなく、通常歯茎の中に隠れている歯根ごと出てくることを意味するため、エナメル質に覆われていないむき出しの歯が登場します。
エナメル質に覆われていないために虫歯や知覚過敏などのトラブルになりやすく、良いことは何もありません。
隣の歯が倒れてくる
奥歯がなくなるとスペースが開くため、それを埋めようと隣の歯が倒れるように傾き始めます。これを「傾斜(マイグレーション)」と呼びます。
斜めになった歯は磨きにくく、虫歯や歯周病などでトラブルが起こりやすい状態になります。また、一度倒れてしまった歯を直すためには全体矯正が必要です。
出っ歯になりやすくなる
大きな奥歯は、顎や噛み合わせを支える重要な柱です。その奥歯がなくなると噛み合わせが深くなるため前歯が強く噛み合うようになり、徐々に出っ歯になっていきます。
滑舌が悪くなる
歯が欠損しているとそこの部分から空気が漏れ、滑舌が悪くなって不明瞭な発音になることがあります。特にサ行やラ行、タ行の音が聞き取りにくくなるでしょう。
咀嚼しにくくなる
奥歯は噛む力の多くを担っています。そのため奥歯が1本欠けることで、何と噛む力が30%〜40%ほど低下してしまうのです。しっかりとものを噛めないままで飲み込むことになり、胃腸に多くの負担をかけます。
顔の形が変わり老化が早まる
奥歯がなくなることで噛まなくなるため、顔の形が変わってきます。奥歯がある側ばかりで噛む癖がつき、筋肉のつき方も変わるため頬がこけ、シワも増えだすでしょう。
全身のバランスが崩れる
頭は体の中で最も重い箇所です。頭蓋骨の位置にズレが生じると、体のバランスが崩れるだけでなく重い頭を支えるために筋肉が緊張し、肩こりや背中痛などのトラブルも発生します。また、徐々に姿勢も悪くなっていくでしょう。
理学療法分野でも、顎の不安定さが姿勢制御に影響することは指摘されています。
認知症リスクが上がる
奥歯でものを噛む行為は、顎の筋肉や神経を通じて脳へ直接刺激を送る重要な役割を果たしています。
東北大学の研究では、歯の残存数が少ない、または咀嚼困難・口腔乾燥といった口腔機能低下がある場合、認知症発症リスクが1.10〜1.20倍(=10〜20%)上昇することが報告されています。
国立長寿医療研究センターも、咀嚼力の低下や歯周病菌が、アルツハイマー型認知症の発症に関与する可能性を報告しています。つまり「噛める状態」を維持することが、認知機能の維持・向上に極めて重要なのですね。
参考:東北大学 大学院歯学研究科(Kusama T 他)「Poor oral health and dementia risk under time-varying confounding: A cohort study based on marginal structural models」
参考:国立長寿医療研究センター「歯周病と認知症の関連について(後編)歯周病と歯周病菌は認知症を悪化する?」
瞬発力が失われる
人間は瞬間的に力を入れる際に、奥歯を食いしばることで体幹を固定します。そのため、奥歯がなくて食いしばれないと体のバランスが崩れ、瞬発力を失ったりうまく力を出せなくなったりします。
また、咀嚼筋の活動は神経伝達のスピードにも影響します。噛む力が弱まると瞬時の判断力・反応速度が落ちるという報告もあります。スポーツ選手が噛み合わせを重視するのはこのためです。
奥歯の抜歯後放置の期間別にみる治療の難易度
奥歯の欠損治療は、そのままでいた期間によって難易度、費用、期間が大きく変わります。
半年以内の放置
半年以内であれば、歯を抜いた穴が治癒し、骨や歯茎が安定し始める時期です。まだ隣の歯の傾きや対合歯の挺出が軽微であるため、ほとんどの場合、比較的シンプルにインプラント、ブリッジ、部分入れ歯のいずれかの補綴治療を開始できます。
1年以上放置
この期間を超えると、歯の移動(傾斜・挺出)が顕著になり始めます。
歯列矯正が必要なケースでは、傾いてしまった隣の歯を部分矯正で元の位置に戻す処置が追加で発生します。これには数ヶ月の治療期間と追加の費用が必要です。
また、噛む刺激がないことによる顎の骨の吸収が進行し始めます。インプラントを希望する場合は骨が足りないと埋入できないため、インプラントを挿入するための骨造成が必要になることもあります。
数年放置
数年単位で放置すると、治療は非常に複雑化します。
挺出した対合歯を大きく削るか、場合によっては抜歯しなければ治療スペースが確保できないことがあります。
また、骨吸収が激しく進行していると、インプラント治療の前に骨造成(GBRやサイナスリフト)という大がかりな外科手術が必須です。これだけで数ヶ月〜半年以上の期間と数十万円の費用が追加で必要になります。
ブリッジを選んでもスムーズにはいきにくいでしょう。 支えとなる両隣の歯が大きく傾斜している場合、ブリッジの設計自体が不可能になることがあるためです。
奥歯の抜歯後はどのような治療がある?

奥歯の抜歯後は、以下のような補綴治療をする必要があります。
- ・インプラント
- ・ブリッジ
- ・部分入れ歯
- ・歯の自家移植・再植
なお、それぞれの費用相場はあくまでも目安としてお考えください。特に健康保険を使わない自費治療は、使う素材やクリニックによって金額に幅が出ます。
インプラント
インプラントは人工で歯根を作って顎の骨に埋め込み、自然な感覚の状態まで回復させる治療法です。自分の歯と同じようにはいきませんが、それでも90%の力で噛めるまで回復します。
| メリット | ・自分の歯のように噛める ・他の歯に負担をかけない ・長寿が長い |
| デメリット | ・外科手術が必要 ・費用が高め ・治療期間が長い |
| 費用相場 | ・自費:30万~50万円程度 |
| 治療期間の目安 | 4ヶ月~1年程度 |
近年は抜歯と同時にインプラントを埋入する「即時荷重インプラント」も登場し、治療期間の短縮が可能になっています。
ブリッジ
ブリッジは欠損した歯の両隣の歯を支えとし、人工の歯を橋のようにかける治療法です。違和感も少なく、自分の歯のようにものを噛めます。
| メリット | ・違和感が少ない ・保険適用で安価(素材による) ・治療期間が短い |
| デメリット | ・健康な両隣の歯を大きく削る ・支台歯の寿命を縮めるリスクがある ・誰でも適用できるわけではない |
| 費用相場 | ・保険:1万~3万円程度 ・自費:5万~80万円程度 |
| 治療期間の目安 | 1ヶ月~3ヶ月程度 |
最近はセラミック系素材を使用したCAD/CAMブリッジが登場し、金属を使わない自然な見た目にすることも可能です。
【関連記事】ブリッジ治療についての記事はこちら
歯を失ったときのブリッジ治療とは? メリット・デメリットや費用相場を紹介
部分入れ歯
残っている歯に針金をかけ、部分的な入れ歯を入れる治療法です。
| メリット | ・保険適用で安価 ・治療期間が短い ・歯を削る量が少ない |
| デメリット | ・噛む力が弱い(自分の歯の20〜30%程度) ・異物感が強い ・定期的な調整が必要 ・バネが目立つ |
| 費用相場 | ・保険:5,000円~2万円程度 ・自費:10万~40万円程度 |
| 治療期間の目安 | 2週間~1ヶ月程度 |
金属のバネで固定する従来型に加え、柔らかい素材のノンクラスプデンチャーなど、違和感を軽減したタイプも増えています。
【関連記事】入れ歯についての記事はこちら
インプラントよりも入れ歯の方が良い? その判断基準とは
歯の自家移植・再植
親知らずや機能していない健康な歯を、抜歯した奥歯の欠損部に移植する治療法です。10〜30代で条件が合えば選択可能で、ご自身の歯を使うため拒絶反応がなく、費用もインプラントより抑えられる場合があります。成功率は患者様の条件に左右されますが、約70〜90%といわれています。
若い方や奥歯の抜歯後すぐに検討できる選択肢です。
奥歯の抜歯後いつ治療すべき? タイミングの目安
抜歯後2〜3か月ほど経過すると歯ぐきと骨が落ち着いてきて、補綴治療がしやすくなります。
このタイミングを逃すと骨吸収が始まり、治療の難易度が上がります。抜歯後そのままにしている期間が長くなるほど費用も増える傾向にあるため、できるだけ早めに歯科医院へ相談することがとても大切です。
もしすでに数年放置してしまった場合でも、再生治療によって回復できるケースもあります。放置してしまったけれどやっぱり治療したいと希望する方は、諦めずに専門医へ相談しましょう。
当院ハピネス歯科では、患者様の状態に合わせた治療法をご提案しています。お気軽にお問い合わせください。
奥歯を失わない・放置しないための予防とケア
奥歯を失うと大きな悪影響が発生することを、お分かりいただけたでしょうか。
奥歯を失ってから後悔しないためには、「抜歯後どうするか」だけでなく、「そもそも奥歯を失わないためのケア」を意識することが大切です。
日常生活の中でできる予防と、抜歯後の正しいケアを行うことで、長く自分の歯で食事を楽しめるようになります。ここでは、奥歯を失わないための生活習慣やセルフケアのポイントをみていきましょう。
抜歯後の生活習慣とセルフケア
奥歯を抜いた後は「もう痛くないから大丈夫」と思ってしまいがちですが、治療を先延ばしにすると口内環境のバランスがどんどん崩れていきます。
抜歯直後は歯茎や骨が回復していく大切な時期です。清潔を保ちつつ、しっかり噛める環境を取り戻す準備をしていきましょう。
まずは食生活の見直しが大切です。
抜歯した側で噛むのを避けてばかりいると、反対側ばかりを使う「片噛み癖」がつき、顎関節や筋肉のバランスを崩す原因になります。柔らかい食事から徐々に両側で噛む練習を始めましょう。
また、歯磨きやうがいも丁寧に行うことが大切です。抜歯後は細菌が入りやすいため、刺激の少ない歯ブラシを使い、優しく清掃してください。歯間ブラシやデンタルフロスで汚れを溜めないようにし、歯周病菌の繁殖を防ぐことが、将来の抜歯リスクを下げます。
そして、痛みがないと「治療を急がなくても大丈夫」と思い込んでしまう方が多いですが、痛みがない=問題がないではありません。
特に奥歯は1本失っても一時的に咀嚼ができてしまうため、放置しやすいのですね。
「いつか治す」ではなく、「今のうちに噛み合わせを守る」という意識を持つことが、長い目で見てご自身の健康を守ることにつながります。
定期的なかみ合わせチェック
定期検診では虫歯や歯石だけでなく、噛み合わせの微妙なズレも確認できます。
歯は1本でも失うと、他の歯にかかる力のバランスが変化します。その結果、歯が揺れたり、詰め物が外れたり、顎の関節に負担がかかることもあるのです。
半年〜1年ごとに歯科でかみ合わせの状態をチェックしてもらいましょう。以下の変化を早期に発見できますよ。
- ・歯の傾き
- ・噛み合わせの高さの変化
- ・顎の動き方の左右差
特に、ブリッジやインプラント・入れ歯などで補った場合は、治療後の再調整も非常に大切です。定期的なメンテナンスを行い、治療した歯を長持ちさせ、次のトラブルを防ぐようにしましょう。
よくある質問(FAQ)
では、奥歯の抜歯後そのまま放置してしまうことに関しての、よくある質問を紹介します。
- ・Q1.痛みがなくても治療は急いだ方がいいですか?
- ・Q2.抜歯してから何年も経っていますが、今からでも治療できますか?
- ・Q3.費用を抑えたい場合、どんな治療がいいですか?
- ・Q4.治療費は分割できますか?
Q1.痛みがなくても治療は急いだ方がいいですか?
A:はい、痛みがなくてもすぐに治療の相談を始めてください。
奥歯の欠損によるリスクは、「痛みを伴わず静かに進行する」ことが最大の問題点です。欠損を放置すると、隣の歯が傾いたり、噛み合っていた歯が伸びてきたりと、お口の中でドミノ倒しのような変化が始まります。
この変化は、やがて矯正が必要になったり、骨が痩せて治療が複雑になったりと、将来的に治療の費用と期間を大幅に増やします。痛みがないときこそ、治療が最も簡単で安価に済む最高のチャンスですよ。
Q2.抜歯してから何年も経っていますが、今からでも治療できますか?
A:はい、ほとんどの場合、今からでも治療は可能です。諦めずにご相談ください。
ただし、期間が長いほど治療が複雑になる傾向があります。数年経つと、歯列矯正(部分矯正)や骨造成(こつぞうせい)などの追加治療が必要になる可能性が高くなります。
治療の難易度や費用は上がりますが、治療を先送りし続けることによる全身への悪影響(姿勢、認知症リスクなど)を考えれば、今が最も早いタイミングです。まずは歯科医院でCTなどの詳細な検査を受け、現在の骨の状態と最適な治療計画を立てましょう。
Q3.費用を抑えたい場合、どんな治療がいいですか?
費用を最も抑えられるのは、保険適用の「部分入れ歯」または「ブリッジ」です。
部分入れ歯は他の治療方法と比べて最も安価で、隣の歯を大きく削る必要もありません。ただし、噛む力は大きく低下し、慣れるまでの違和感が大きいのがデメリットです。
ブリッジの費用目安は保険適用の場合で1万円〜3万円程度です。安定感は入れ歯より優れますが、欠損部の両隣の健康な歯を削って土台にする必要があります。
ただし、安価な治療法でもメンテナンスや再治療に費用がかさみ、結果的にインプラントよりも高くなるケースもあります。ご自身のライフスタイルや残りの歯の健康状態を考慮し、歯科医師とよく相談してくださいね。
Q4.治療費は分割できますか?
はい、自費診療(インプラントや一部のブリッジ・入れ歯)の場合、多くの歯科医院で分割払いに対応しています。
分割の方法としては、クレジットカードによる分割払いとデンタルローンがあります。まずはカウンセリングで総額を確認し、ご希望の支払い方法について遠慮なくご相談ください。
奥歯を抜歯したら必ず補綴を! 歯の数を守って健康を維持しよう
奥歯を抜歯したら、噛む機能を復活させるための治療を必ず受けるようにしてください。たとえ部分入れ歯など「噛む力が弱いケース」であっても、歯がなくまったく噛めないことに比べると、はるかに良い結果になります。
歯の健康は全身の健康につながります。今は奥歯が1本なくても影響がない状態であったとしても、やがて必ず悪影響が出て、さまざまなトラブルに対処しなくてはならなくなるでしょう。
トラブルがない内に欠けた歯の埋め合わせをし、噛む機能を取り戻してください。早めの歯科予約がおすすめです。